1.支えあい
会内の仲間同士で悩みを共有、話合い、解決への道筋を励まし合いながら 一緒に考え、元気を取戻せます
.jpg)
2.学びあい
直面している問題をテーマとした事例学習会、研修会、講演会他、学びの場を企画・開催、多くの実用知識を学びます
(例)
①疾患の知識や対処法、支援サービス、福祉制度等の活用事例学習会
②「親なきあとの備え」(住まい、生活支援サービス、成年後見制度他)
.jpg)
3.地域交流
地域交流イベントへの積極的な参加、開催協力・支援、当会広報活動他

4.働きかけ
行政機関、関連団体との当会活動と課題の共有、制度充実化を働きかけていきます
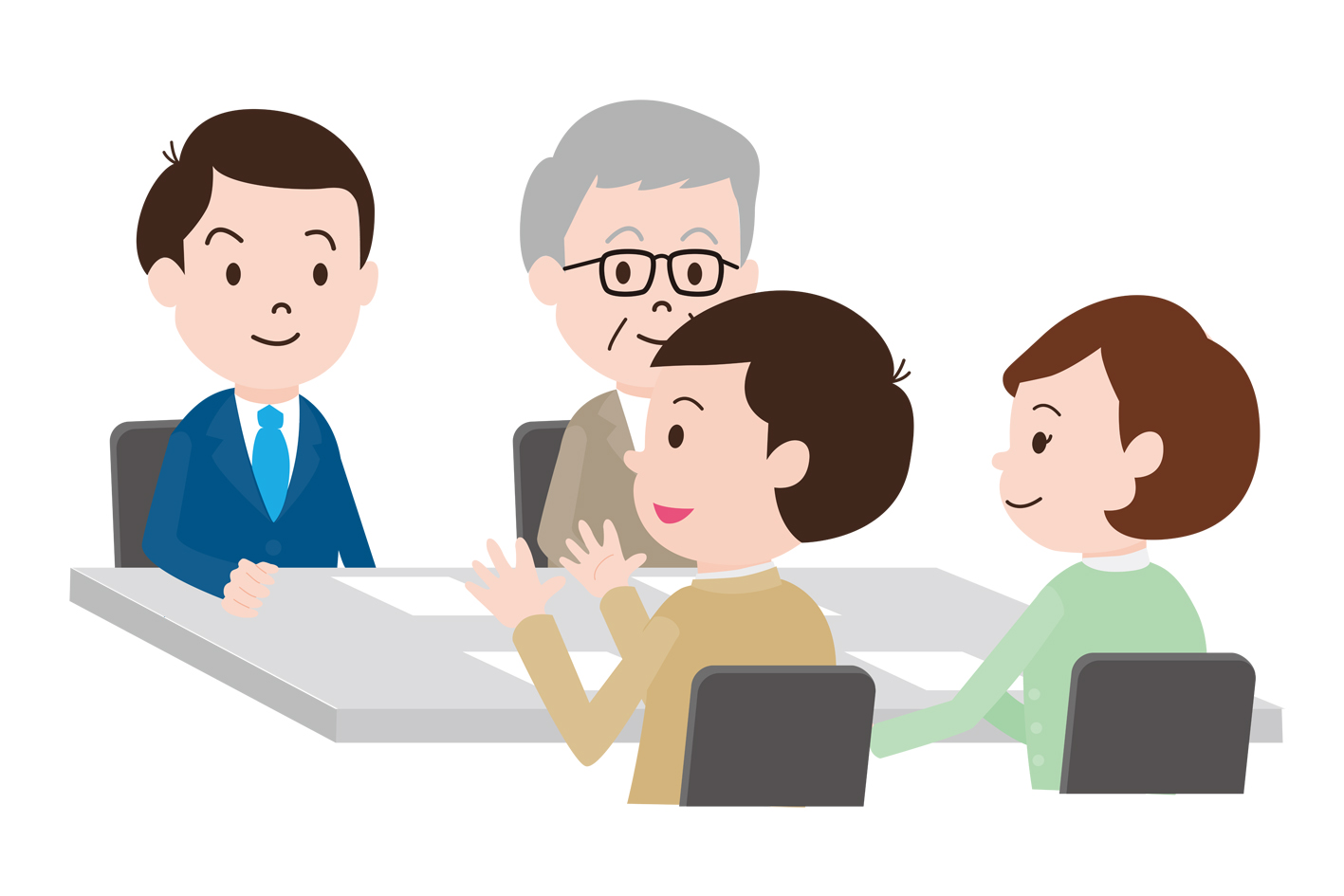
学習活動(その1)井戸端会議 & 事例学習会
≪会議の主旨と概要≫
- 参加者が日頃の苦労や悩み、辛い思いを同じ境遇の仲間同士が安心して話合い、励まし合い、 支え合う交流と対話の集いです
- 参加者は精神障害者を抱える会員家族や各地域のご家族、そして、各地域行政の担当部署、社協の担当者、支援関係者も参加頂き、現実の悩みや課題等の実情の共有、改善要望他、様々な質疑応答、意見交換がなされる対話集会です

≪R6〜R7年度前半期の実施内容:会合で取上げた主なテーマや話題事例です≫
- R6/7〜9月 井戸端会議(定期対話集会)
*8月の活動は休止(猛暑時期のため会員健康面を考慮)- 親なきあとのと当事者の経済基盤について : 生活保護-世帯分離の関係性、年金や福祉制度について
- 当事者・家族間の意思疎通への悩み : 当事者が感情的となり会話が困難、親にあたる等、体験体験談
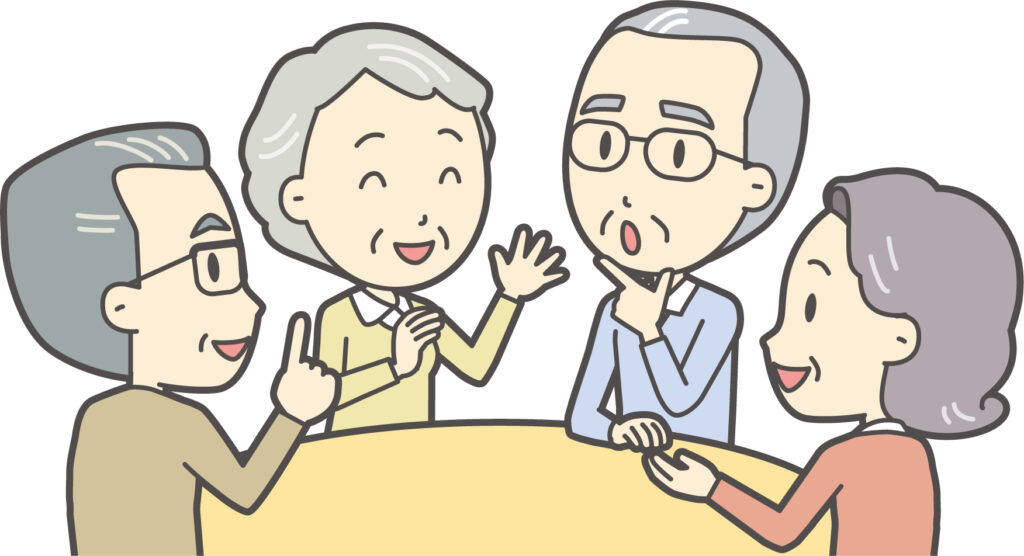
- R6/12月(事例学習会)
- テーマ:当事者への実際の住まい・生活支援事例についての学習
- 講師:GH・相談支援事業所の専門相談支援スタッフ
- 内容:講師による事例紹介、参加者のとのQ&A、意見交換等を実施・・・GHの生活での支援状況や一人暮らしの当事者への支援等 について
- R7/5月 井戸端会議 参加者夫々の直面する悩み(課題、問題)や思いの共有、解決への道筋へのディスカッション~参加者ひとりひとりの悩みや思いに目を向け話し合いを続け感極まる方もおられ、優しさと熱のこもった2時間の対話集会でした
- R7/6月 井戸端会議 今回は、ある男性会員の方からのお話がありました。会社員時代に当事者が発症し、毎日追われる仕事中で当事者に向かう時間を持たなかった自責の念、日常の当事者への対応は結局配偶者が請け負う状態にしてしまったこと、リタイア後の当事者支援への心の内等々のお話いただくなど非常に活発な対話となりました
- R7/7-8月 井戸端会議は来所開催の為、異常なほどの猛暑の中での移動による会員の健康への影響を考慮、急遽この期間の開催は休止としました
- R7/9月 井戸端会議 厳しい残暑とはいえ井戸端会議を再開。 休止期間中の状況など各参加者より発言いただき、以降、A.Bの2グループに分け、グループ対話とし 最後に各グループ代表者より対話内容の発表を行い全員で内容を共有、終了としました。(親なきあとへの備え、服薬管理、定まらない診断への対応他)
学習活動(その2)研修会(講演会・ワークショップミーティング)
≪研修会の主旨と概要≫
- 井戸端会議や日頃のご家族同士の話題をふまえ、具体的な問題、課題をテーマとし、専門家講演とQ&Aで家族にとり実用知識の学習と習得の集いとして実施しています
- 参加者は井戸端会議・事例学習会同様に当会内外の地域の当事者家族を対象とし、ZOOM利用による講師遠隔講演、学習動画 の利用、また、行政や団体主催の研修会への開催協力先として参加等、専門家講演と質疑応答による学習プログラムです
- 保健所、各地域行政主催の研修会、県内専門職団体等の研修会に講師として、シンポジストとして参加するなど学習・研鑽の機会に幅広く参加もさせて頂いております
≪R6~7年度前半の実施内容:会合で取上げた主なテーマや話題事例です≫
- R6/9 動画視聴学習会 そうかいプログラム「なぜ精神疾患当事者は親に当たるのか」
- 教材動画作成者:大阪大学 蔭山准教授 当事者・家族双方の思いと実情についての調査踏まえた学習動画
【参加者感想】
- 当時の当事者及び家族による体験、心理状況等、理解できた
- 動画が体験や現状と重なる部分多く、対処法等、大いに参考となった

- R7/2 講演会
- 那珂市主催「成年後見制度講演会・シンポジウム」参加:障害法務専門弁護士の公演とシンポジウム
- ひたちなか保健所主催(当会は協力団体)講演会
テーマ:「障がい者の未来への経済的な備え」身近なデータを活用し、障がい者本人の将来資金検討方法を講師(FP)より説明頂き知識を習得

- R7/4月 ピアサポーター講演会とワークショップミーティング
(テーマ)「私のリカバリーストーリー」
【講師】茨城県精神保健福祉会連合会 理事 多田公樹様(ピアサポーター) - R7/8月 ひたちなか保健所主催「令和7年度心の健康づくり講演会」(ひきこもり対応について)に参加、 講演後に当家族会の紹介説明を行う
- R7/10月 県社会福祉士会県央ブロック研修会に参加予定(当会にて当事者家族の実情や要望事項のプレゼンと意見交換)参加予定
地域行政機関や関連団体との課題・問題共有と連携促進
【活動報告】 活動報告・意見交換の適宜実施
≪目的≫当事者家族の実情・課題(要望事項)の共有、意見交換、政策・制度改善への反映
➡共生可能な地域社会の実現への努力

【相互の連携と対話促進】
- 当会学習事業へ行政機関・関連団体より講師派遣による福祉制度理解等の当会学習支援
- 学習事業への参加者として出席頂き、当事者家族と直接対話・交流を実践頂く・・・家族の実情(”生の声“)の共有を促進、制度改善や政策へつないでいく
【課題例】
- 親なきあとの備え(関連福祉制度、成年後見制度他、生活・経済的支援制度他)
- 緊急(状況急変)時の当事者及び家族への支援体制
- 相談支援体制について(生活自立や就労活動への相談支援の仕組・制度等)
(関係先)ひたちなか市、那珂市、東海村の障がい担当部署、各地域社会福祉協議会等
当事者・家族・地域社会との交流促進
- 精神障がいへの地域の理解促進と啓発活動への参加
・・・障がい者支援団体開催交流イベントへの定期的参加- フリーマーケットへの参加:地域一般市民理解促と啓発の促進
- 地域障がい者団体のスポーツ大会参加:障がい者との相互交流
- 精神保健福祉会連合会(県内家族会連合会)
・・・県内当事者・家族参加による文化祭
- ボランティア活動への協力参加
今年も赤い羽根共同募金活動参加予定(11月)

他地域家族会との交流・協力関係促進
【目的】
- 当家族会活動の検証と改善による活動の質的向上
- 他地域家族会同士の協力関係強化
【交流内容】
- 共通課題・問題の共有・対応意見交換、先進事例の学びと当会活動へ反映
- 先々の地域超えた活動協力実現への相互協力関係の促進
【活動例】
- 県南地域家族会との定期的な情報・意見交換による家族会活動研鑽と協力関係促進(奇数月第2月曜日の定例交流会・・・龍ヶ崎・取手・牛久・つくば等の交流会に参加)
- R7.7月さいたま市もくせい家族会との交流会(オンライン交流会実施)
- R7.9.6 年度全国精神保健福祉会連合会全国大会(開催地:京都)に参加
地域の精神保健福祉への当会の要望事項
- 多職種専門家チームによるアウトリーチの医療対応の制度・仕組みの構築
ひきこもりや頑なに受診拒否をする当事者を家族が医療施設に連れていくの困難- 多職種専門家(医師・看護師+相談スタッフ他)チームの訪問医療による適切な対応
- 中長期的にはピアサポーター加え本人のリカバリーへの支援も含めた包括的支援チーム活動の仕組を構築、本人への「地域社会での生活中心」とした精神保健福祉促進につながるものと考えるため
- 「親なきあと相談室」の各地域配置で家族及び当事者の事前・事後の相談支援の実現
- 親なきあと、本人の安全な自立生活が可能か⁉・・・が、親の心配事項。 障がいの種別を越えた共通する課題への支援として、地域における包括的支援体制の一環として「親なきあとの相談」機能の整備が重要と考える (例) 大分県「親なきあと相談~安心して生活するために~」
- 「マル福」の精神障害者保健福祉手帳2級保持者・JR・主要私鉄運賃割引の完全適用の実現
手帳保持精神障がい者の大部分は2級、低所得の為苦しい経済状況にあり、完全適用をお願いしたい - 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム(「にも包括」)の具体的な検討状況の情報提供
- 「にも包括」と既存の精神保健福祉制度や新たに計画されている制度・仕組みなどについて
- 制度・仕組みの構築作業の進捗状況と今後の推進スケジュール等について当制度は、当事者の自立した社会生活を支える重要な仕組み・制度であり重要事項と認識しているため
- ピアサポータ―養成制度の構築とサポート事業の実践
同じ疾患体験を有しリカバリーを遂げた方々(ピア)による当事者支援は、気脈を通じた支援となり効果が大きい
